Valery Gergiev & Wolfgang Sawallisch
 「いつも舞台に上がるときは緊張するのに、今度はワクワクしながら舞台に上がることができた」(ティンパニー・小山理恵子)。「引きずり込まれるような体験ができてよかった」(第一バイオリン・小林佳奈)。今、世界で最も注目される指揮者、ワレリー・ゲルギエフの指揮の下、「ペトルーシカ」(ストラヴィンスキー作曲)の演奏を終えた直後の感想だ。二人とも二十歳前後だろうか、額に汗がにじんでいる。
「いつも舞台に上がるときは緊張するのに、今度はワクワクしながら舞台に上がることができた」(ティンパニー・小山理恵子)。「引きずり込まれるような体験ができてよかった」(第一バイオリン・小林佳奈)。今、世界で最も注目される指揮者、ワレリー・ゲルギエフの指揮の下、「ペトルーシカ」(ストラヴィンスキー作曲)の演奏を終えた直後の感想だ。二人とも二十歳前後だろうか、額に汗がにじんでいる。
「受け継がれる情熱の響き」というドキュメンタリー番組を見ていたときのことだ。
今年7月、札幌で行われた「パシフィック・ミュージック・フェスティバル(PMF)」で、世界中から集まった音楽家の卵120人が、一つのハーモニーを作り上げる過程を追った番組だ。オーディションで選ばれただけあって、一人一人はそれなりの腕をもっているが、しょせん「卵」は「卵」だ。なかには、オーケストラはこれが初めてという者もいる。表現力は未熟だし、全員が一丸となって感動を呼ぶ演奏をする域に達していない。
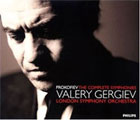 それを、4週間かけて一流の音楽家たちが特訓するわけだが、圧巻は本番前日のゲルギエフ自身によるリハーサルだ。たった一回のリハーサルだというのに、奇跡が起きる。120人が奏でる音が一つの「響き」となる。「音」から「音楽」へ、そして「感動」へと変身するのだ。
それを、4週間かけて一流の音楽家たちが特訓するわけだが、圧巻は本番前日のゲルギエフ自身によるリハーサルだ。たった一回のリハーサルだというのに、奇跡が起きる。120人が奏でる音が一つの「響き」となる。「音」から「音楽」へ、そして「感動」へと変身するのだ。
そんな奇跡を自分も体験したことがある。
* * *
今から40年以上前のことだ。中学生の頃だったと思う。当時、所属していた「朝日ジュニアオーケストラ」*の合宿が箱根であった。小学生から高校生を中心とした子供たちのオーケストラだ。だから、日比谷公会堂や上野の文化会館での演奏経験があるとはいえ、そのレベルたるや推して知るべしだ。
* 朝日新聞社が全国に展開したこのジュニアオーケストラの支部、「朝日ジュニアオーケストラ横浜教室」が「神奈川県青少年オーケストラ」として発足したのが1963年だから、ひょっとしたら、この合宿は「神奈川県青少年オーケストラ」に名を変えた頃だったかもしれない。
 さて、その年の夏季合宿に特別ゲストとして招かれたのが、ウォルフガング・サヴァリッシュ。N響の名誉指揮者として日本でもよく知られている巨匠だ。屋外にしつらえた指揮台に彼が上がり、タクトを手にした。曲は、ベートーベンの交響曲第5番か、モーツアルトの交響曲第35番「ハフナー」のいずれかだったと思う。それからの1時間は…いや2時間かもしれないが、まさに奇跡の連続であった。
さて、その年の夏季合宿に特別ゲストとして招かれたのが、ウォルフガング・サヴァリッシュ。N響の名誉指揮者として日本でもよく知られている巨匠だ。屋外にしつらえた指揮台に彼が上がり、タクトを手にした。曲は、ベートーベンの交響曲第5番か、モーツアルトの交響曲第35番「ハフナー」のいずれかだったと思う。それからの1時間は…いや2時間かもしれないが、まさに奇跡の連続であった。
信じられない響きが、ハーモニーの渦が湧き上がり、広がりはじめたのだ。
「ウソ!自分たちのオーケストラがこんな音を出せるなんて!」。子供ながらにも、自分たちの力量は自分たちが一番よく知っている(と思っていた)。だから、それが自分たちには絶対に出せない音であり、響きであることは明らかだった。なのに、それは厳然として響きわたり、周りの木々を揺るがしている。
脊髄に電流が走った。
本人すら気づかない潜在能力を一人一人から引き出し、それを響きへ、感動へとまとめ上げる。それが名指揮者なのだ。半世紀近く経った今日でも、あのときの不思議な興奮は鮮やかに蘇ってくる。
* * *
そこにはおそらく、経営者やリーダーのひとつの理想形がある。箱根でのあの貴重な体験を生かせていないどころか、そうした理想形にあまりに程遠い自分をみるにつけ愕然とする。果たして自分には、「サヴァリッシュ先生、ありがとう」と言える日が来るのだろうか。

 種明かしをしよう。アフリカの国、ブルキナファソの首都である。11世紀に成立したワガドグ王国の都として築かれた都市だが、そもそも「ワガドゥグー」という地名の由来は、行商人を意味する「ワガ」と村を意味する「ドゥグー」の合成語とする説がどうも一般的だ。昔からこの地は交易の拠点であったようだ。
種明かしをしよう。アフリカの国、ブルキナファソの首都である。11世紀に成立したワガドグ王国の都として築かれた都市だが、そもそも「ワガドゥグー」という地名の由来は、行商人を意味する「ワガ」と村を意味する「ドゥグー」の合成語とする説がどうも一般的だ。昔からこの地は交易の拠点であったようだ。 実はこのティンブクトゥ、奇しくもブルキナファソの隣国、マリ共和国にある古都の名前だ。ティンブクトゥはその近づきがたさのため、英語では以前から、「エキゾチックで遠い土地」とか「地の果て」を意味する隠喩として使われていた。それに着目したのが、ソフト開発会社の
実はこのティンブクトゥ、奇しくもブルキナファソの隣国、マリ共和国にある古都の名前だ。ティンブクトゥはその近づきがたさのため、英語では以前から、「エキゾチックで遠い土地」とか「地の果て」を意味する隠喩として使われていた。それに着目したのが、ソフト開発会社の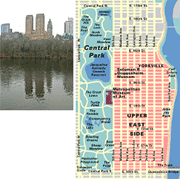 当時NYT本社で研修を受けていた僕をAbe(エイブ)が自宅に招待してくれたのだ。たしか1977年のはずなので、エグゼクティブ・エディターに就任した翌年。飛ぶ鳥を落とす勢いのあった時期だし、エイブが帝王として君臨していた頃だ。
当時NYT本社で研修を受けていた僕をAbe(エイブ)が自宅に招待してくれたのだ。たしか1977年のはずなので、エグゼクティブ・エディターに就任した翌年。飛ぶ鳥を落とす勢いのあった時期だし、エイブが帝王として君臨していた頃だ。 が、なによりも驚いたのは、招待客の顔ぶれの豪華さだ。全員の顔を覚えているわけではないが、僕の左に座ったのが、
が、なによりも驚いたのは、招待客の顔ぶれの豪華さだ。全員の顔を覚えているわけではないが、僕の左に座ったのが、